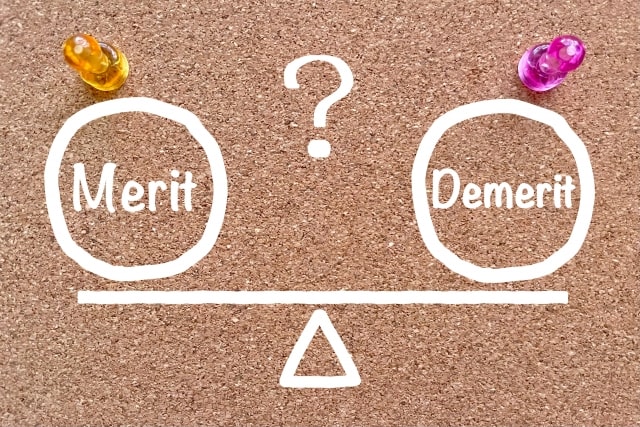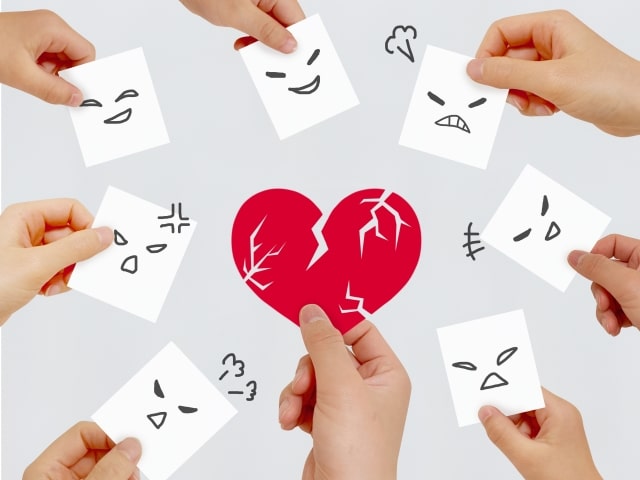関連記事
-
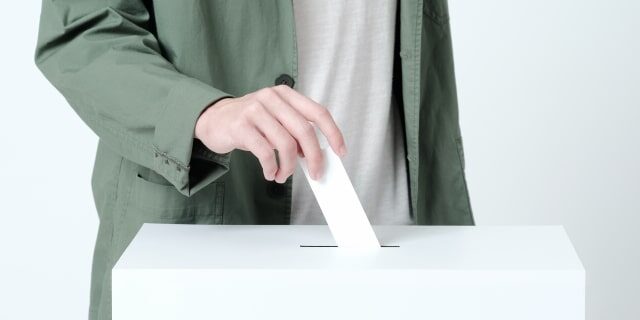
知的障害のある息子の投票 ~AI活用で選挙支援~
息子には自閉症・ADHDに加えて、中度の知的障害があります。18歳になってから初めての選挙で投票所入場券が自分あてに届いたときは、大人の仲間入りができてうれしかったのか、張り切って投票に行きました。よ …
2025.08.27
-

通常学級について思うことー20年の学習塾経営経験から
発達が気になる子どもが、通常学級(普通学級)に在籍した場合 私の息子には 知的障害があるので、学校時代は特別支援学校、特別支援学級の両方を経験しました。 小学校1・2年生 特別支援学校 小学3~6 …
2023.04.05
-

特別支援学校高等部の心配ごと
■特別支援学校高等部を卒業しても中卒扱い? 知的障害を伴う自閉症の息子は現在22歳です。中学校時代は特別支援学級に在籍していました。高校は義務教育ではありませんから、普通高校に、支援級はありませ …
2023.03.08
-

重度の知的障害のある方の地域移行 ~施設から故郷への物語~
先日、社会保障審議会障害者部会の報告書「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて」(案)が提出され、改めて現状の制度や仕組みについて,新たな提言がなされました。その冒頭、基本的な考え方として、 …
2022.10.12
おすすめの記事
-

発達障害のある人が健康に気をつけるべき理由と対処法
発達障害のある人が二次障害で精神疾患になりやすいのはよく言われる話です。しかし、実は発達障害のある人は、精神的疾患だけではなく発達障害の特性からくる内科領域の病気にも要注意なんです。私も妊娠により毎月 …
2026.01.29
-
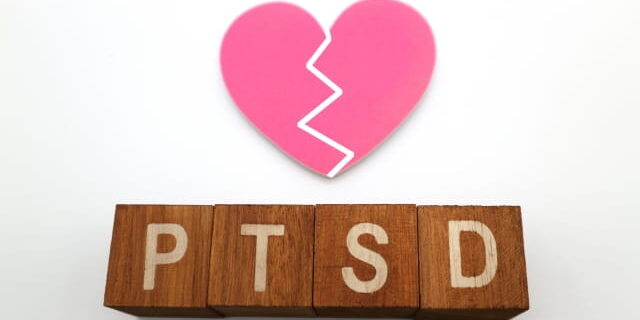
発達障害がある私のPTSDについてお話しします~阪神・淡路大震災から31年の歩み
私は、発達障害(ASDとADHD)とPTSD(心的外傷後ストレス障害)を抱えています。今年1月、私のPTSD発症の大きな要因となった阪神・淡路大震災から31年が経過しました。いまだに症状と向き合う日々 …
2026.01.21
-

忘れ物力
お子さんが定型発達なのか、注意欠如・多動性障害(ADHD)なのかはわかりませんが、自分の子どもに対して「だらしない。忘れ物ばかりしている。時間を守らない。一体どうしたらよいか」と嘆いている人がいます。 …
2026.01.15
-

どう向き合う? 発達障害のある子の服薬拒否
病院で薬を出されたけれど、子どもがどうしても飲めない。そんな悩みを耳にすることがあります。飲ませなくては治療にならないと焦ったり、強い口調で指示してしまったり。服薬は毎日のことだけに、壁にぶつかると本 …
2026.01.07