関連記事
-

発達障害のある人が健康に気をつけるべき理由と対処法
発達障害のある人が二次障害で精神疾患になりやすいのはよく言われる話です。しかし、実は発達障害のある人は、精神的疾患だけではなく発達障害の特性からくる内科領域の病気にも要注意なんです。私も妊娠により毎月 …
2026.01.29
-

忘れ物力
お子さんが定型発達なのか、注意欠如・多動性障害(ADHD)なのかはわかりませんが、自分の子どもに対して「だらしない。忘れ物ばかりしている。時間を守らない。一体どうしたらよいか」と嘆いている人がいます。 …
2026.01.15
-

どう向き合う? 発達障害のある子の服薬拒否
病院で薬を出されたけれど、子どもがどうしても飲めない。そんな悩みを耳にすることがあります。飲ませなくては治療にならないと焦ったり、強い口調で指示してしまったり。服薬は毎日のことだけに、壁にぶつかると本 …
2026.01.07
-
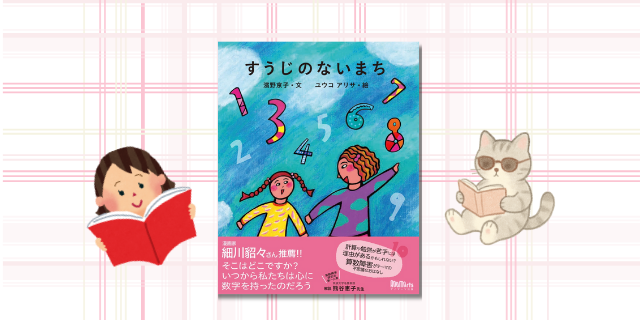
算数障害当事者が絵本『すうじのないまち』を読んでみた
発達障害の代表的なものに、 注意欠如・多動性障害(ADHD)、自閉スペクトラム症(ASD)、そして(LD・SLD/学習障害・限局性学習障害) があります。 書店や図書館に行くとADHDやASDの本は多 …
2025.12.03
おすすめの記事
-
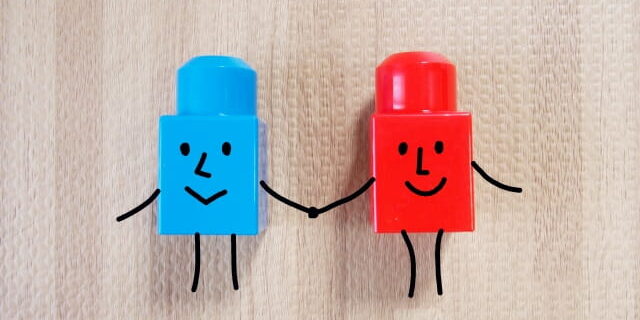
赤ちゃんはどこからくるの?知的障害や発達障害のある子への性教育を考える
息子に障害があると分かったとき、心配事のひとつに性の問題がありました。将来女の子を追いかけ回したりしないか?手を出して捕まったりしないか?――同じようなことを思ったことのあるママもいらっしゃるのではな …
2026.02.10
-

発達障害のある人が健康に気をつけるべき理由と対処法
発達障害のある人が二次障害で精神疾患になりやすいのはよく言われる話です。しかし、実は発達障害のある人は、精神的疾患だけではなく発達障害の特性からくる内科領域の病気にも要注意なんです。私も妊娠により毎月 …
2026.01.29
-
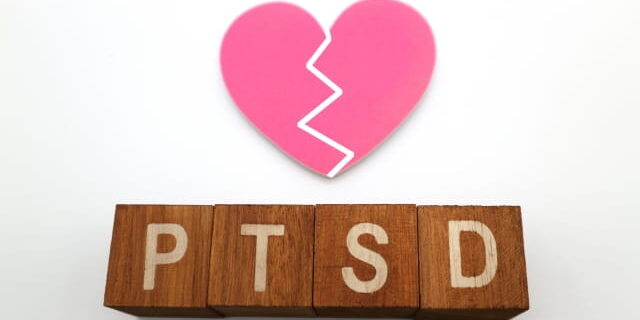
発達障害がある私のPTSDについてお話しします~阪神・淡路大震災から31年の歩み
私は、発達障害(ASDとADHD)とPTSD(心的外傷後ストレス障害)を抱えています。今年1月、私のPTSD発症の大きな要因となった阪神・淡路大震災から31年が経過しました。いまだに症状と向き合う日々 …
2026.01.21
-

どう向き合う? 発達障害のある子の服薬拒否
病院で薬を出されたけれど、子どもがどうしても飲めない。そんな悩みを耳にすることがあります。飲ませなくては治療にならないと焦ったり、強い口調で指示してしまったり。服薬は毎日のことだけに、壁にぶつかると本 …
2026.01.07




